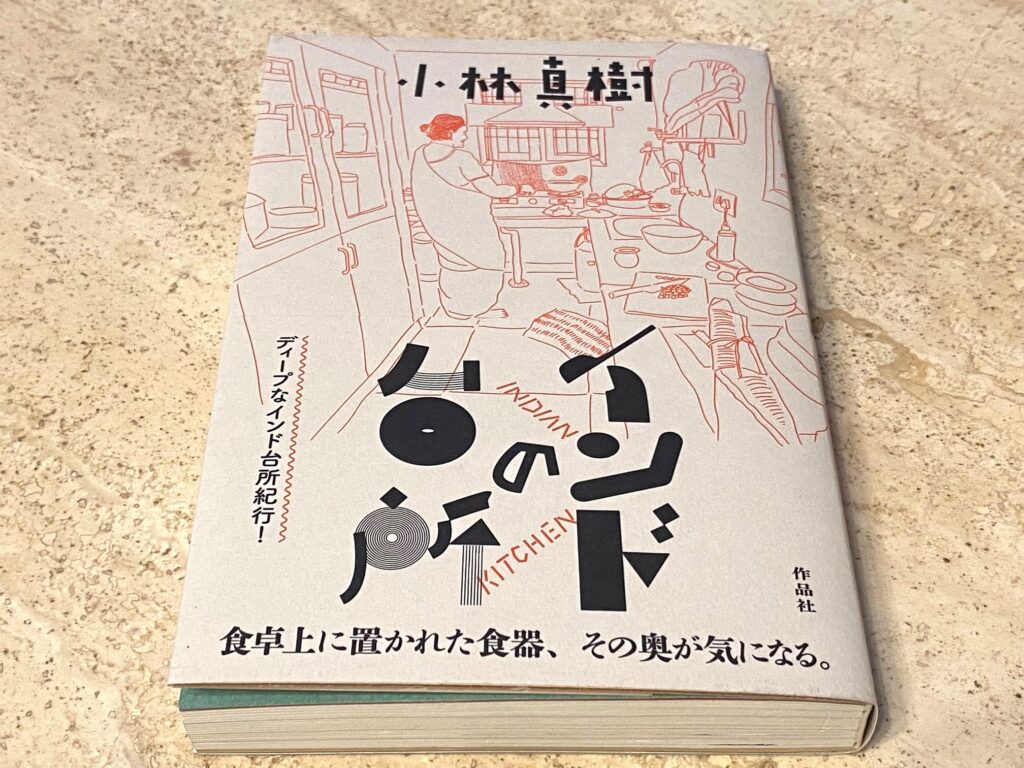日本のインド・ネパール料理店
小林真樹著
阿佐ヶ谷書院
2022年3月1日初版発行
発売日である2月24日に心待ちにしていた本書が配達されました。
「おわりに」で著者の小林真樹氏が以下のように記されています。
現代日本のインド料理店の主たる担い手が、インド人ではなくネパール人であるという事実は今や広く知れ渡っています。しかしネパール人の経営するインド飲食店、つまりインド・ネパール料理店(しばしばインネパ店と略されます)は、インド人ではない事で亜流視され、その総数に比して料理や動向が顧みられる事も、フォーカスされる事もありませんでした。しかしそこには現代日本のインド料理店像を象徴する動態が確かに見られ、深堀りしていくうちに単にインド人の代替ではない豊かで独自の食文化の広がりや、それを支えるネパール人オーナーやコックたちのたくましくも人間臭い魅力が沁みてきます。こうした動向や実態を紹介したいと思ったのが、本書執筆の主たる動機です。
北から南までのインド・ネパール料理店のネパール人オーナーやコックさんたちの物語が記されています。
コラム「越境するダルバート」では、ダルバートという呼称がいつ頃から日本で使われるようになったか、またダルバートではなくカナセットなどの呼称を使う店もなぜ多いのかなど興味深い話が並び、
元来看板すらないバッティで単に空腹を満たすだけの存在だったダルバートは、やがて従来持つイメージを脱却し、タメル地区でチャレスの皿に載せられて提供されるご馳走と化した。そうしたイメージの越境に加えて、国境を越えた日本ではやがて人種の壁を越えたインド人コックによって日本人に提供されるメニューとして作られるようになる。本国ではあまりにも身近過ぎて「カナ」や「パート」など複数の呼び名が併存し、非統一だった呼称が日本人の間で「ダルバート」の呼称に収斂され、一メニューとして提供されるようになる。我々のテーブルの前で食べられるのを待つその一皿は、形や味を変え、様々な境や壁や概念を越えて今、そこに存在しているのである。
と締めくくられています。
コラム「ネパール人の店名考」では
良くも悪くも文字に込める思い入れが過剰な日本人に比べ、ネパール人のそれはあまりにもあっさりしていて驚かされる。特に店名に関して、我々日本人からすると狙いもゲン担ぎも熱い想いもなく、そのあっさり具合はまるでその対象への情熱の欠如をすら感じさせるものがある。その辺り、当のネパール人たちは一体どう思っているのだろう。
から始まり、店名についての様々な考察が綴られています。
さらに最後には、
『日本のインド・ネパール料理店の成り立ち』が、
①草創期~ネパール人の来日
②増殖期~玉石混交と試行錯誤の時代
③成熟期~ネパール料理店の成立と今後の動向
の各章でまとめられていますが、ネパールの食文化も含めた文化を語る上でのカーストの問題や、社会情勢の変化の歴史を語る上でのマオイスト運動の話など、避けて通れない話にも触れられています。
関西のインド・ネパール店も『絢爛たる美食世界~京都・大阪・兵庫』と題して、「ヤク&イエティ Yak & Yeti」さん、「アジアンガーデンダイニング アサン Asian Garden Dining ASAN」さん、「ネパール創作料理 シュレスタ Shresta」さん、「ネパールのごちそう jujudhau ズーズーダゥ」さん、「ナラヤニ NARAYANI」さん、京都の 5つの「タージマハル」さん(ナマステ・タージマハル、タージマハル・エベレスト、ニュー・タージマハルエベレスト、バグワティ・タージマハル、エス・タージマハル)が取り上げられています。
マオイスト運動に関する書籍は
→「現代ネパールの政治と社会-民主化とマオイストの影響の拡大(南真木人、石井溥編集) 明石書店」
ネパールのカーストの文化人類学的考察の書籍は
→「みんなが知らないネパール 文化人類学者が出会った人びと 三瓶清朝著 尚学社」