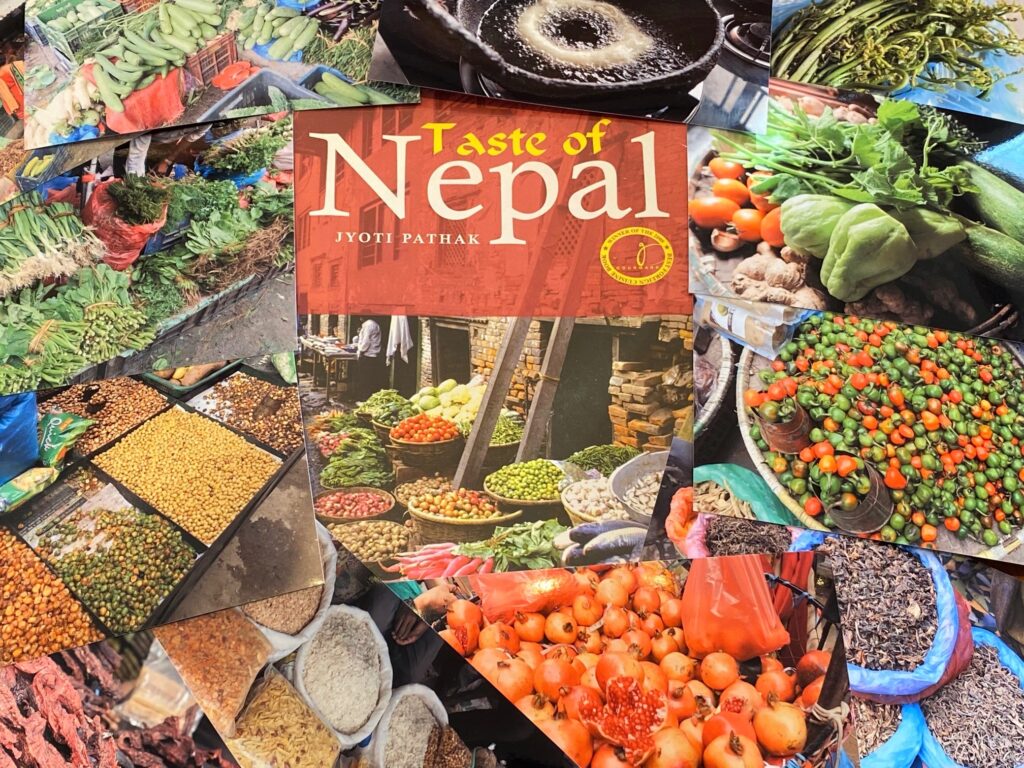スリランカ政治とカースト
N.Q. ダヤスとその時代 1956~1965
川島耕司著
芦書房
2019年2月25日 初版第1刷
1956年の総選挙で S.W.R.D. バンダーラナーヤカが「シンハラオンリー」政策を掲げて選挙戦を戦い、勝利したこと、そしてその妻シリマーウォー・バンダーラナーヤカがシンハラ仏教ナショナリズムに基づく政策を遂行し続けたことがスリランカにおける民族対立の深刻化に大きく寄与したことは明らかである。そしてそのどちらにおいてもカラーワの行政官であった N.Q. ダヤスはきわめて重要な役割を果たした。
と「あとがき」で記されているように、本著はシンハラ社会にあると言われる 15の代表的なカーストのうち最高位にあるゴイガマ (Goigama) ではなく、カラーワ (Karava) の N.Q. Dias ダヤスに焦点が当てられています。
ヒンドゥ教が主たる宗教のインドやネパールの社会のカーストは良く知られていますが、スリランカの社会のカーストについては、まず『はじめに』で、以下の様に説明されています。
スリランカ社会のもつ明確な特徴の一つは、カーストに言及すること自体が強力なタブーであることである。カーストはセンシティブな話題であり、日常会話のなかでは極力回避され、公的な議論のなかにもほとんど登場しない。スリランカ政治においては、個人の権利、女性の権利、あるいはエスニックーマイノリティの権利という議論は登場するが、マージナルな地位におかれたカーストに属する人々の権利という概念はほぼ存在しない。逆に、カースト間の平等に関する問題を提起しようとする試みはしばしば非難や叱貞、あるいは侮蔑の対象となる。カーストを扱うことは、マナー違反であり、不必要で時代遅れであるとされる。あるいは、社会的結束への脅威であるとされ、意図的な社会的分断の手段であるとみられることさえある。
その結果、カーストに関わる問題があったとしても、著しく過小評価される。カーストに関してはスリランカ社会は十分に平等主義的であるとされ、カーストを識別することには意味がないというのが「スリランカ全体に渡る標準的な反応」となっている。
とは言え、ブッダの教えそのものはカーストを否定するものですが、シンハラ人の仏教徒の間にもカーストは確実に存在してきました。
『第1章 スリランカのカーストとカラーワ』では、比較的新しい時期に南インドからスリランカに渡来した集団と考えられるカラーワを中心に、カーストについて記されています。ゴイガマより低い地位にあるとみられていたカラーワは、植民地下のプランテーション経済において、アラックなどの酒類流通などで富を蓄積し、その経済力を背景に社会的威信や政治的影響力を求めるようになります。
経済的に圧倒的な成功を収めたカラーワのエリートたちは、社会的地位の上昇と政治的影響力の拡人を求め始めた。仏教復興運動への支援はその一環であった。この運動はもともと植民地下でのキリスト教宣教師の活動への反発から生まれたものである。
しかし 1931年にドノモア憲法により男女普通選挙が導入されると、人口でも多数を占めるゴイガマが政治的支配をさらに強化し、カラーワの政治的影響力の欠如が明確となりました。
『第2章 1950年代スリランカにおける政治とカースト』では、1950年ごろのシンハラ・カーストに関し綴られています。
明らかに 1950年頃のシンハラ社会にはカーストの社会的、政治的影響は大きく残っていた。カースト規制を強制するような行為は徐々に行われなくなっていたとされるが、人々の意識においては、「地位の記憶」が強固に残り、生活をさまざまな形で規定していた。
自らのカースト内で結婚するという内婚規制が非常に厳格に守られ、食物に関する規制もまたかなり強く残っており、カースト・ヒエラルキーは厳然と存在し、低位カーストは高位カーストに対してさまざまな形で経緯を示さなければならない時代でした。
その1950年代の非ゴイガマ・カーストの注目された政治家を取り上げています。カラーワ・カーストのクララトネ Patrick de Silva Kularatne 1893-1976 は仏教復興運動の重要な成果として設立された中等教育のエリート校、アーナンダ・カレッジのみでなく、スリランカの「ほとんどあらゆる仏教徒学校」の発展に尽力しました。しかしその後の政界進出は無残なものとなりました。サラーガマ・カーストのダ・シルワ Charles Percival de Silva 1912-1972 は院内総務および国土および国土開発大臣に任命されました。1960年の総選挙ではスリランカ自由党を率いて戦いましたが敗北に終わりました。
非ゴイガマの政治エリートたちが政治的影響力を確保することは少なくともゴイガマのエリートたちに比べれば明らかに難しかった。クララトネやダ・シルワが必ずしも十分に彼らが望む政治的活動ができなかった少なくとも一因にカーストの問題があったことは十分に想定できるのではないだろうか。少なくとも当時のスリランカ政治の観察者たちの多くにはそう思われていた。P・ダ・S・クララトネは、教育者として華々しい成功を収めながら、統一国民党内では「完全に無視」されることになった。サラーガマのC・P・ダ・シルワは、スリランカ自由党内ではかなりの地位にまで上りつめたのだが、首相になることはできなかった。カーストが彼らの政治的活動をどの程度制約したかは必ずしも明らかではない。しかし、ゴイガマが圧倒的多数を占める政界においては非ゴイガマ・カーストの政治家たちは不利であるという認識は当時の人々の間にはかなりの程度あったことは確かである。
それではこうした状況のなかで政治的野心をもつ非ゴイガマのエリートたちはどのように行動しうるのだろうか。どのような選択肢がありえたのであろうか。当時強力に台頭しつつあったシンハラ仏教ナショナリズムに深く関わり、より高次なアイデンティティにコミットすることでカースト的制約を乗り越えようという戦略はその一つになりうると思われる。
『第3章 1956年の政治変革』では、独立から1956年の政治変革に至る時期におけるシンハラ仏教ナショナリズムの展開をたどり、N.Q. ダヤスという行政官に焦点をあててカラーワ・エリートたちの動きを明らかにしようとしています。
このように 1950年代前半には仏教と政治が深く結びつき、仏教僧や在家信者たちの間での組織化が進んだ。ただすでにみたように、当時注目された「コミュナリズム」はムスリムやキリスト教徒といった宗教的コミュニティを標的にしたものと「インド人問題」に対するものであった。マジョリティであるシンハラ人仏教徒の側からセイロン・タミル人を激しく批判するような動きは 1950年代半ばになるまでは明確には現れなかった。逆に、自国語運動 (Swabasha movement) においてはシンハラ語とタミル語の二言語をともに公用語化すべきであるという見方がかなりあった。少なくとも 1950年代初頭にはそう主張する人々は多かった。
後にシンハラ・オンリーを激しく主張することになるS.W.R.D. バンダーラナーヤカ白身もまたタミル語をも公用語にすべきであると述べていた。
その中でダヤスは、カトリック教徒が比較的高い教育を受け、多くの要職を占め、教会を中心に組織化されていることにその政治的影響力の一因があることに注目し、同様に仏教徒も組織化されるべきと考え、シンハラ仏教ナショナリズムに深く関わっていきます。
つまり1950年代前半にはシンハラ仏教ナショナリズムが相当程度高められ、統一比丘戦線を代表とするいくつかの組織ができあがったが、この動きを組織化し、より影響力のある政治勢力として提示する役割の大きな部分を担ったのはダヤスであり、ダヤスときわめて密接な関係にあったメッターナンダ、あるいは仏教委員会の一員でもあるクララトネといったカラーワの活動家たちであった。もちろん 1950年代における仏教僧たちの政治意識の高まりや、在家信者たちへのシンハラ仏教ナショナリズムの浸透が彼らだけの力によるものではないことは明らかである。特に1930年代以降、シンハラ人仏教徒としてのアイデンティティと政治はますます密接につながりつつあった。しかしダヤスたちがきわめて精力的にその流れを組織化し、また促進したこと、そして彼らがそうすることで一定の政治的影響力を確保しようとしたことは間違いないのではないだろうか。
『第4章 S.W.R.D. バンダーラナーヤカとシンハラ仏教ナショナリズム』では、1956年に総選挙で勝利し成立したバンダーラナーヤカ政権下における、政治、宗教、ナショナリズムの展開が記されています。
政権獲得後のバンダーラナーヤカは、特に言語政策に関しては過激なシンハラ・ナショナリストの要求を極力排除しようとした。彼はタミル語話者たちとの会談に長い時間をかけた。後述するように、彼はタミル人指導者セルワナーヤガムとの間で分権化に向けた協定を結んだ。ただ、いったん煽り立てられた民族感情をコントロールすることは明らかに困難であった。
1956年6月5日に提出された公用語法案は、基本的にはシンハラ語を唯一の公用語とするものでしたが、マイノリティへの譲歩を含むものでした。過激なナショナリストたちには到底受け入れることが出来ないものであり、その圧力により改変されることとなり、タミル人たちによる「サティヤグラハ」という抗議活動と、その後の反タミル暴動を招くこととなり、スリランカにおける民族対立が深刻化していきました。
基本的に融和的な政治姿勢をとろうとしたバンダーラナーヤカを激しく非難した 1人がカラーワ・カーストの L.H. メッターナンダでした。N.Q. ダヤスと共にシンハラ仏教ナショナリズムに深く関与し、バンダーラナーヤカを勝利に導いた 1956年の選挙戦において仏教僧を組織した重要な人物でした。N.Q. ダヤスが新政権成立後文化局長として政府内において一定の役割を果たしたのに対し、L.H. メッターナンダは政府職に就きませんでした。
両者の関係が実際にどのようなものであったかは必ずしも明らかではないが、ダヤスがその財力と影響力によってメッターナンダの言論活動を支えていたという可能性は十分にあると思われる。イギリスの政府文書には、メッターナンダは N.Q. ダヤスの「表看板 (front man)」であるとも記されている。
公用語法案の他にも、バンダーラナーヤカは自らの「政治的手腕」によりマイノリティにも配慮した政策を遂行しようとしました。1957年の BC協定もそのひとつです。
BC協定(バンダーラナーヤカ・セルワナーヤガム協定、Bandaranaike-Chelvanayakam Pact)はバンダーラナーヤカとスリランカ・タミル人を代表する連邦党の S.J.V. セルワナーヤガムとの妥協の上に成立したものであった。この協定のなかでタミル人たちはタミル語をシンハラ語と同等の地位にあるものとして扱うよう求める要求を放棄した。また彼らはそれまで進めてきたサティヤグラハ運動を停止するとした。一方で政府は、タミル語をマイノリティの言語として扱い、北部や東部の行政機関で使用することを認め、また、教育や農業、あるいはシンハラ人のタミル地域への入植を管理する権限を地域評議会に与えるというものであった。両者の合理的な妥協の上に成立したこの協定は民族問題解決に向けての出発点としては非常によくできたものであったとみられている。しかし議会内の両陣営からは激しく攻撃されることになった。
メッターナンダをはじめとして、このBC協定批判が繰り返され、シンハラ人とタミル人の対立はますます激しいものとなり、1958年には大暴動も発生しました。そのような状況の中、1959年9月にバンダーラナーヤカが暗殺されます。「バンダーラナーヤカ暗殺」の項では、暗殺の首謀者とされるブッダラッキタの人物像や政界との入り組んだ人間関係が記されています。この暗殺には不可解な部分も多く、さまざまな憶測が流れましたが、首相の妻であったシリマーウォー・バンダーラナーヤカが首相となり、結果的にみれば過激なシンハラ仏教ナショナリストたちにとっては明らかにより好ましい状況がもたらされました。
「確固とした自らの政治哲学は全くもたず」、シンハラ至上主義的心情に疑問をもつことも、それを隠すことをもしなかったパンダーラナーヤカ夫人は、過激なシンハラ仏教ナショナリストたちにとっては明らかに好都合な指導者であった。「狂信的な在家信者 (fanatical layman)」と呼ばれた L.H. メッターナンダや「仏教への熱狂者 (Buddhist zealot)」と評された N.Q. ダヤスらにとっては、彼女の夫に比べれば、はるかに与しやすかったであろう。実際、バンダーラナーヤカ夫人の政権の下でシンハラ人仏教徒の要求に沿う政策が次々と採用されていった。特にダヤスはシリマーウォー・バンダーラナーヤカ政権初期においてその職務を超えた影響力を発揮することになる。メッターナンダは民間の団体などを通じてその動きを支援した。
『第5章バンダーラナーヤカ夫人政権と N.Q. ダヤス』では、予期せぬ形で、そして政治的経験をほとんど欠いた状態で政治の場に登場することになったシリマーウォー・バンダーラナーヤカについてまず述べられています。
1960年の総選挙では「過激な戦闘的仏教徒諸団体」が彼女を支援したのであるが、彼女は首相就任後そうした勢力の要請に応えることに夫のようには躊躇しなかった。そのため過激なナショナリストたちは「彼ら自身の目的を達成するために利用可能な手段を新政権のなかでとうとう獲得した」と感じたのであった。実際、彼女の態度は特にシンハラ仏教ナショナリズムへの対応に関しては夫のそれとは大きく異なっていた。前章でみたように、彼女の夫はステーツマンシップを発揮してコミュニティ間の融和を図ろうとした。少なくとも彼は努力した。しかし彼女にはそのような意図は初めからほとんどなかったようにみる。
彼女のスリランカ自由党政権は、外国人の権益とマイノリティ・コニュニティ、主にタミル人とローマ・カトリック教徒に対する差別的方策を導入しました。私立学校の国有化により、カトリック教徒の学校が大きな影響を受け、シンハラ語化政策がより徹底的に推し進められ、公務員におけるシンハラ人の数は大幅に増えました。軍隊と警察も急速にシンハラ化されました。
もちろんこうした彼女の政策はタミル人からの反発と抵抗を招いた。バンダーラナーヤカ夫人の「非妥協的な熱意」によって国の危機はより深刻なものとなっていった。明らかに彼女の政治姿勢はタミル人のなかに暴力的な集団を生み出した一因となった。彼女は「タミル人の軍事的闘争の母」だともいわれた。そして1960年代前半の彼女の政権内で、おそらくもっとも強い影響力をもっていたのが N.Q. ダヤスであった。
ダヤスがどのようにバンダーラナーヤカ夫人に近づいたのかは必ずしも明らかではありませんが、夫人に重用され「自由裁量権」とまでいわれる権力を持ち、仏教徒の地位向上や仏教の国教化を目指すことになります。
いずれにしても N.Q. ダヤスはバンダーラナーヤカ夫人の側近として強力な権力を行使することになった。彼はさまざまな事項に積極的に関わった。特に、軍隊や警察の運用、政府の移民政策において強い影響力を発揮した。彼はたとえば行政組織のなかに「活動的な仏教徒団体」を設立することを進め、そして軍隊への採用は事実上 100パーセントをシンハラ人仏教徒にするよう努めた。そうすることで、「歴史的理由によって非仏教徒や非シンハラ人がこれまでもってきた圧倒的な支配力」と彼がみなすものを打ち破ろうとしに。彼が打ち倒すべき対象であると考えたものの一つに植民地時代につくられた教育制度におけるキリスト教徒の優位性があったことは明らかであった。
1962年にはそのような政治に対する大きな危機感を抱いた、高位の士官と警察によってバンダーラナーヤカ夫人や N.Q. ダヤスらを拘束しようとするクーデター計画が立てられましたが、発覚し未遂に終わりました。この未遂事件は、軍や行政などの公的機関のさらなるシンハラ化、仏教徒化を促しました。「戦闘的な仏教徒の団体」とされる民間団体の BJB (Bauddha Jathika Balawegaya 仏教徒国民軍)が設立されたり、仏教の斎日であるボーヤ日(満月、新月、二つの半月日)を休日にする運動が行われるようになりました。両者に N.Q. ダヤスが深くかかわっていたとされます。
その後、経済状況の悪化の中で次第に生き詰まっていったバンダーラナーヤカ夫人の政権は 1964年12月に議会を解散、1965年3月の総選挙では野党であった統一国民党が政権を担うことになりました。N.Q. ダヤスは国防外交常任長官の任を解かれることになります。1966年2月には新政権に対するクーデター計画が発覚しましたが、もっとも疑われた一人が N.Q. ダヤスでした。もし成功していればダヤスを中心とした政権が生まれた可能性も否定できません。
『おわりに』では第1章から第5章までのまとめが記されていますが、本書が明らかにしようとしたカースト問題については
シンハラ仏教ナショナリズムというより高次なアイデンティティ、あるいはイデオロギーに訴えることで、カーストという特殊性、あるいは非ゴイガマであることの限界を N.Q. ダヤスは乗り越えようとしたように思える。この戦術はより過激なナショナリズムを提示し、行動することによって、あるいはその帰結として民族的な対立がさらに激しくなることによって明らかにより有効に機能した。ダヤスはシンハラ仏教ナショナリズムに基づく政策の実現を強力に求めるという点で一貫していた。
さらに、
19世紀後半からの仏教復興運動への非ゴイガマ・エリートたちの積極的な関与もまた、より高次のアイデンティティを主張することでカースト的制約を乗り越えようとする試みであったともいいうる。
別言すれば、これはカーストに対峙するのではなく、カースト的なものを回避、無視、あるいはある意味で隠蔽することでカーストを乗り越えようとする試みであったということもできるかもしれない。
と述べています。
++++++++++++++++++++++++++++++++
シンハラタミルの対立については、反政府武装組織「タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)」と政府が相対し、長らく内戦状態にあったこと位の知識しかありませんでした。本書を読むと、その関係を悪化させたバンダーラナーヤカ夫人政権における施策、及びこれまで明らかにされることの無かった非ゴイガマカーストのN.Q. ダヤスの果たした役割りをよく理解できます。
林明 スリランカのシンハラとタミルの対立『社会科学ジャーナル The Journal of Social Science』43 (1999) には、BC協定批判の解説として
これはパンダーラナーヤカ・チェルヴァナーヤカム協定と言います。ここでうまく収めておけばまだよかったのですが、今度は僧侶が出てきまして、これはシンハラ人に対する裏切りであるなどという演説をし、また野党側のジャヤワルダナという人が、キャンデイまで協定反対の行進をした結果、パンダーラナーヤカはせっかくまとまった協定を58年 5月に破棄してしまったのです。これは、実はとても大事な構図でして、つまり与党が民族問題解決案を提示すると、野党はそれに同意せずに、民族問題を与党攻撃のための政治の道具として利用して、与党の民族問題解決の試みには協力しないという構図です。
と記されていますが、J.R. ジャヤワルダナが 1944年にシンハラ語を公用語とするという動議を国家協議会に提出した時は、後にシンハラオンリーを主張することになるバンダーラナーヤカはそれに反対したとの本書の記述を読み直すと、さらに深い理解となります。